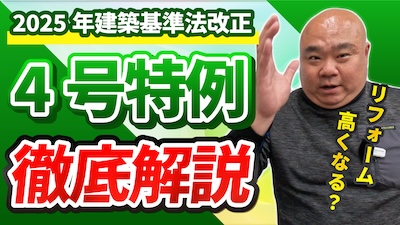みなさんこんにちは!
今日は2025年4月以降に適用される建築基準法の改正について、わかりやすく解説していきます!建築基準法の改正…正直、ちょっと難しそうですね…。でも安心してください!
今日は、今回の改正の中でも、目玉となっている、一般消費者の皆さまへの影響が大きい『4号特例の縮小』にしぼって、できるだけわかりやすくお話しします!
これからリフォームや建て替えをご検討されている方にはかなり影響があると思いますので、ぜひ最後までご覧ください!それでは解説して参ります
目次
今回の改正の影響は
結論からお伝えすると、今回の改正では、冒頭でお話した「4号特例の縮小」により、木造住宅のリフォームや修繕において、今まで必要なかった申請が必要になります。
その申請作業のために、工期が今までより長くなったり、申請にかかるコスト加算されて工事費用が高くなることが予想されます。
そのため、2025年4月以降にリフォームや修繕工事を計画されている方は、この辺りに十分注意して進めていく必要があります。
影響が大きいとされている、『4号特例』は何ですか?
4号特例とは、<「2階建て以下」「延床面積が500㎡以下」の木造住宅など、一定の条件をクリアする建物については、建築確認および検査の審査を一部省略する>とされている特例です。
これが2025年4月以降に着手がはじまる工事より、縮小されます。
手続きが難しくなるだけならいいのですが、それだけではなく、今までよりも設計の確認が厳しくなり、それに対する費用や期間が増える可能性が示唆されているんですね。
ちなみに、なぜ4号なのでしょうか?
建築基準法では、建築物を4つに分類しています。1号~3号は大規模な建物で、4号は木造2階建てや平屋など、小規模な建物を指します。
4号特例の具体的な変更内容
まずは、今回の変更で「対象となる建物」について解説します。図をご用意しましたので、ご参照ください。
こちらの図のように、これまで木造平屋建て・木造2階建ての建物については、4号特例により大規模リフォームの確認申請が不要とされていました。
日本のほとんどの住宅がこの2種類に当てはまるので、これまで「リフォームのときに確認申請をする」というイメージすらあまりなかったのです。
ところが、今度の変更により、「木造2階建て」や「延べ面積200㎡超の木造平屋建て」では確認申請が必須になります。
ほとんどの一般住宅は200㎡を超えないため、平屋の場合はよほど広さがない限り、確認申請なしでさまざまなリフォームができると考えて良いでしょう。
一方、今までと状況が変わるのが、木造2階建てのリフォーム。2025年4月以降は増築だけでなく、さまざまなリフォームで確認申請が必要になります。
どのようなリフォームが対象になるのか
つぎに具体的にどのようなリフォームが対象になるのか解説します!4号特例の縮小により、申請対象になる工事が大幅に増えました!まずは図をご参照ください。
木造2階建て住宅において「大規模リフォーム」に分類される柱、床、階段、屋根、外壁などを半分以上工事する場合は、確認申請の対象となります。「半分以上」とは具体的には、総面積に占める割合や、柱などの場合は総本数に占める割合を指します。
そして、逆に、キッチン、トイレ、お風呂などの水回りのリフォームや手すりやスロープなどの設置工事については、従来通り確認申請が不要となります。
概要はこのような感じですが、実際には、「カバー工法による改修は申請不要」や「改修範囲が構造部分に及ぶため申請が必要」など、より細かい基準がありますので、工事業者に対象となるか否か、必ずご確認ください。
自分の工事が対象か、否か、は、国土交通省が発行している資料のフローチャートがわかりやすいのでこちらもご参照ください。
4号特例の縮小がもたらす影響
特に次の3つのケースでは確認申請の手続きに時間を要し、これまで発生しなかった追加費用がかかる可能性がございます。
構造の把握が困難な物件
1つ目は、図面がなく、構造の把握が困難な物件 です築年数が経過した中古物件などで、図面が紛失している場合が該当します。このような場合、確認申請の前に壁や天井を一部解体し、内部の構造を調査する必要が生じる可能性があります。
現行の法規に適合していない物件
2つ目は、現行の法規に適合していない物件 です
過去に法令に適合しないリフォームが行われていた物件や現在の法規には適合しない物件などが該当します。このような場合、現行の基準に適合させるために、想定外のリフォーム費用が発生する可能性がございます。
再建築不可物件
そして3つ目のケースとして、最も大きな影響を受けるのが「再建築不可物件」です。再建築不可物件とは、既存の建物を解体すると、新たな建築が認められない物件を指します。
これは、特に道路に近い家などが該当します。「接道義務」とよばれる災害時に消防車や救急車が通れる広さを確保する義務によるため、です。
これまでは、再建築ができないため、建物を残したまま間取り変更や構造補修を行うことで、快適な住環境を維持する方法が一般的でした。
しかし、今後、これらの間取り変更にも確認申請が必要となります。これにより、接道義務を満たさない再建築不可物件では、確認申請が通らず、希望するリフォームが難しくなる可能性がございます。
「原状回復工事」や「解体工事」への影響
改正により、当然、リフォームに伴う解体工事でも対応すべき申請作業が増えます。
たとえば、経年劣化した壁・柱・床・梁・屋根・階段などを半分以上を改修する原状回復工事や、内装スケルトン工事などでも、構造部分を解体するため、申請に対象となります。逆にクロスの張り替えなどは、構造部分にあたらないため、申請は不要です。
リフォームを考えている人の対処法は?
まずは、依頼を予定している、工務店や施工業者にに早めに相談しましょう。もしそれでも不安がある場合は、改正に向けて、行政側が各種相談窓口を設けていますので、市役所などに確認してみましょう。
また、業者側の皆さまは、国土交通省が設けている業者向けの相談窓口である「建築士サポートセンター」で相談することができます。
建築士サポートセンター
https://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_001025.html
まとめ
最後にまとめです。
建築基準法改正により、
・2025年4月以降に着工する木造住宅の大規模リフォームにおいて、今まで必要なかった確認申請が必要になります。
・申請作業のために、工期が長くなったり、申請にかかるコストで工事費用が高くなることが予想されます。
・主な対象となる建物は、木造2階建て、対象工事は大規模リフォームで、水回りなどの小規模リフォームは対象外です。
今後の動向も注目しながら、しっかり準備していきましょう!